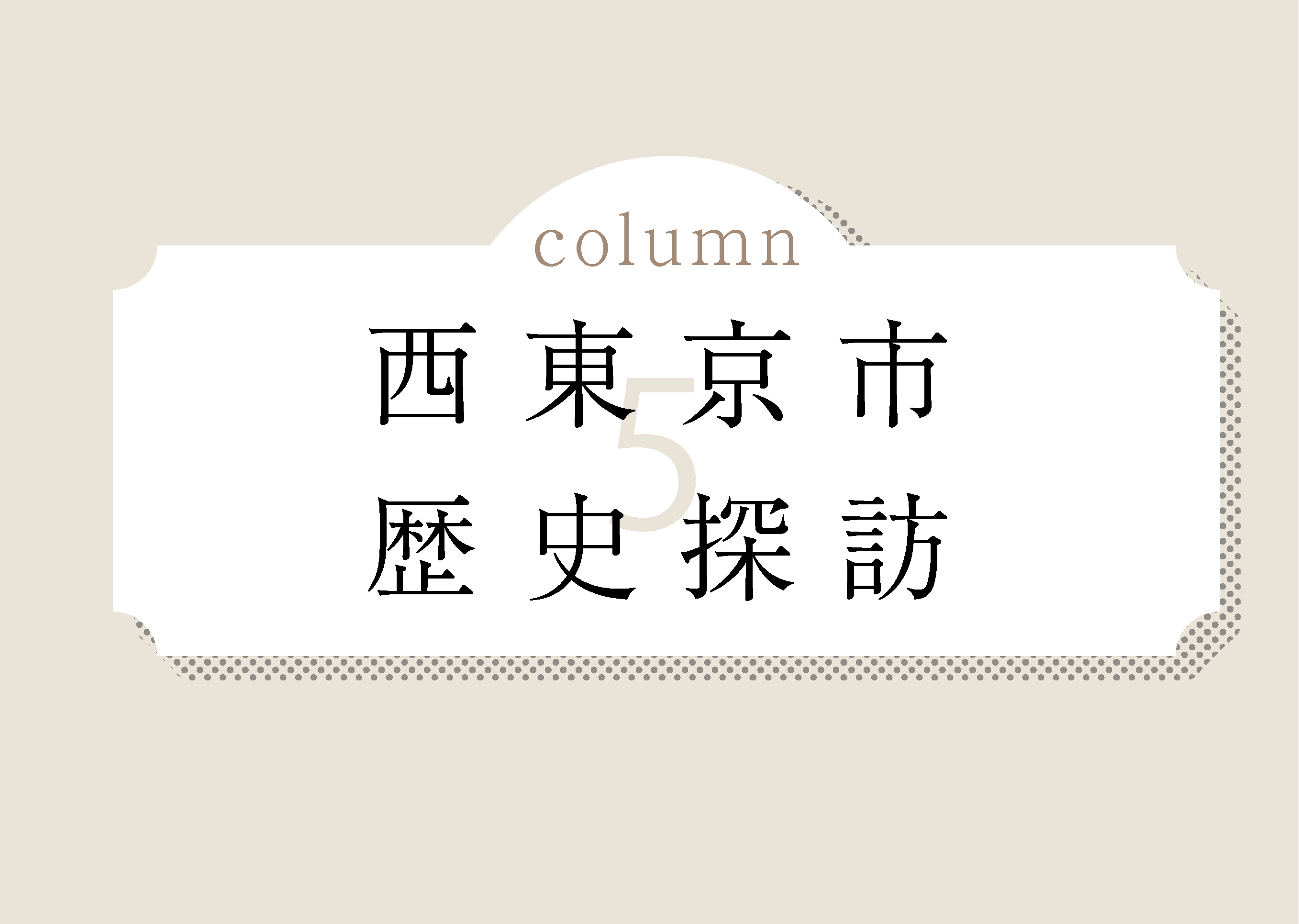
滝島俊の西東京市歴史探訪⑤。今回は千駄山と東伏見稲荷神社のお話です。
保谷八景「千駄の秋景」
保谷八景って聞いたことありますでしょうか? 明治の頃、保谷に見られた美しい景色を称えて言い伝わった八か所の風景です。その中の一つが「千駄の秋景」で、現在の東伏見公園・東伏見稲荷神社付近から眺める秋の景色でした。
現在の東伏見公園一帯は、以前は「千駄山」と呼ばれる地で、石神井川によって作られた河岸段丘の北側高台にあたります。
かつては、この一帯には葦(アシ・ヨシ)やススキが生い茂り、これらの束が千束(千駄)も作れるような場所でした。ここからの眺めは、秋になり黄金に輝く稲穂や、紅に染まる葦の穂、白いススキの穂、松の緑、小沼の碧など色とりどりの風景が楽しめたようです。
時代は移り過ぎ、昭和2年(1927)に旧西武鉄道村山線(現西武新宿線)が開通し上保谷駅(現東伏見駅)が開業します。
それに先立つ大正14年(1925)、旧西武鉄道は駅周辺から石神井川にかけての広大なエリアの土地を取得し、そのうちの25、000坪を早稲田大学に寄付し、グラウンド誘致に成功します。また、住宅地開発と稲荷神社の勧請も同時に行う都市開発を行いました。
東伏見稲荷神社は、明治維新で東京が首都となり、関東地方の稲荷信仰者が東京にて参拝できる京都伏見稲荷の分霊社を、との希望によって創建されたものです。この勧請にあたっては、旧西武鉄道が土地7、000坪を無償貸与し、建立にかかる費用のうち3万円(当時)を提供しました。東伏見稲荷神社は昭和4年(1929)に落慶し、同時に「上保谷駅」は「東伏見駅」に改称されました。当時は参拝客で賑わったそうです。東伏見稲荷神社は今でも商売繁盛の神様として厚く信仰されています。

東伏見公園の沿革
西武バス及び関東バスに「千駄山住宅」という停留所があります。これはこの地に都営住宅があった名残なのですが、実は千駄山一帯は都営住宅ができるかなり前から公園用地としての活用が検討されていた場所でした。
戦前の昭和16年1月(1941)に『武蔵野都市計画区域では空地・緑地が急速に減少しており、保健・衛生・防空上憂慮される状態にある』という理由で公園が計画されました。おそらく南部にあった中島飛行機の工場なども計画に影響していると思われます。終戦後、住宅不足を補うため都営千駄山住宅となり周辺も宅地化が進みましたが、当初の計画から58年後の平成11年(1999)に都市計画が変更され、公園面積13・7haとする都立公園計画が再開されました。
公園は未だ建設途上ですが、既に明治の昔の「千駄の秋景」を彷彿とさせる景色を見ることができるようになってきました。千駄の葦は姿を消しましたが、ここから拝む初日の出や、西の空に夕日が沈むとき富士山が見せるシルエットは格別なものがあります。

※掲載の情報は取材当時のものです。
※本サイト掲載の記事‧写真‧イラスト等の無断転載を禁じます。




